
今年も種から育てている定番の夏野菜のトマトですが、まだ植え付け時期には少し早いですが苗がかなり育ってきたのでさすがに定植してあげないといけない状態です。
昨年も十分な収穫ができましたが、トマトに追われるほどの収穫量ではなかったので今年は少し苗を多めに植えてトマトを堪能したいと考えています。
トマトといえばコンパニオンプランツとしてバジルを混植するのが定番ですが、今回はマメ科野菜も一緒に混植して畝の多様性にも配慮していきたいと考えています。
ということで今回はトマトとコンパニオンプランツの定植について紹介します。
トマトの畝は牛糞たい肥・鶏糞・もみ殻を入れて土壌環境を整えておく

うちの家庭菜園の場合は基本的に前作の野菜が押していてなかなか畝があかないため、畝を立てたらすぐに定植してしまいます。
畝たてしてから定植まで1~2週間ほどあけるのが普通なんだと思うのでこのやり方は苗にとってはいびつな土壌への定植となって少しストレスになっているんじゃないかと思います。
それでも、特にどの野菜も病気になることもなく元気に育ってくれているのでひとまずこのままで様子見としています。
今回の畝たてで入れた土壌改良材はこちら。
- 牛糞たい肥:有機物の追加
- 鶏糞:元肥
- もみ殻:長期的な有機物の追加
だいたいどの野菜の畝でもこの組み合わせですが、畝を耕して元肥だけを追加していては土がやせてくるので牛糞たい肥を入れて有機物を補います。
同じように有機物を補う目的でもみ殻も入れますがこちらは牛糞たい肥ほどすぐには効いてこないので、もっと長い目でみた場合の土壌改良材になります。
もみ殻はライスセンターでもらえたり、購入できたりするので安く大量に準備しておくと大活躍しますよ。
元肥は基本的には鶏糞を入れています。
トマトは果菜類なので元肥としてはリンを入れておきたいところだと思いますが、有機栽培をしているので化成肥料でピンポイントな施肥というのができません。
とはいっても鶏糞は即効性も高く、リンも多く含まれているので元肥としてのチョイスは間違っていません。
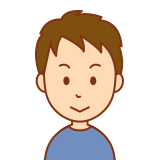
うちは肥料は鶏糞しか使っていないのでリンが多いのを狙ったわけではありません。
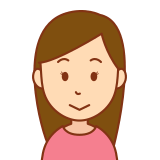
単純に有機肥料かつコストパフォーマンスの高いものが鶏糞しかない
っていうのが正直な理由よね。油かすは高くて…(泣)
トマトの定植方法

うちの場合はトマトは株間距離を30cmくらいを目安に定植していきます。
一般的なトマトの植え付け間隔は40~50cmくらいですので若干密植気味に植え付けることになります。
畑作業は基本的に週末しか時間が取れないので脇芽はガッツリ摘み忘れて大きくなってしまうため、30cm間隔で植え付けるとわけが分からないくらいに茂ってしまいます。

毎年こんな感じのうっそうとした感じになってしまうので大変ですが、それでも収穫量は増えるのと思ったほど味が悪くなることもないのでこんな感じで栽培しています。
ポットのトマトの苗をばらす

1株ごとに丁寧に育苗できればいいのですが、避ける時間が限られているので毎回1つの育苗ポットで3株くらいの苗を育てています。
今回は定植していくのでポットの苗を1株ごとにばらしていきます。
トマトの苗は絡まりあってどうにもならないほどの根張りではないのでまだばらしやすくて楽ですね。
ポットに複数の苗を育てていて、定植のタイミングでばらす場合のデメリットは植え付けからしばらくは苗が萎れてしまいやすいことです。
根がつくまでは水分の吸い上げがうまくいかないのでどうしてもしおれがちです。
天気の良い日に定植する場合はこまめに水やりしてあげないと枯れてしまう可能性もあるので要注意です。
定植直後の水やりの手間を減らしたかったり、枯れてしまうリスクを抑えたいなら育苗ポットには1株だけ育てるようにしましょう。
株間距離30cmでトマトを少し深植えする

トマトの苗は株間距離30cmを目安に定植していきます。
先ほども述べましたが、うちのトマト栽培は株間距離も近く脇芽もかけずに放任栽培のようになってしまうためかなりの密植状態となります。
トマトは脇芽を土に差していれば根が出るような強い野菜なので植え付けは少々深くなってもかまいません。
土に埋まった茎の部分からは発根してくるので寝かせ植えという茎を横に倒して植える方法もありますよ。
定植したら支柱を立てますが毎年、大雨でトマトの支柱が倒れてしまっているので今年は竹の支柱を使わずに全部ホームセンターで購入した園芸用の支柱を使いました。
本当は竹の支柱を使いたいのですが、強度不足で倒れてしまうくらいなら園芸用支柱を増やしていこうという判断です。
トマトのコンパニオンプランツを混植する

トマトのコンパニオンプランツといえばバジルが有名ですが、よく調べてみてもバジルが吸水性の高い野菜だからトマトに余分な水分がいかず甘く成長しやすい程度の情報しか載っていません。
まぁ、それでもメリットはあるわけなのでまずはトマトのコンパニオンプランツとしてバジルを選んでおきます。
次に、トマトはたくさんの果実を成らせる野菜ですので肥料もたくさん必要となります。
肥料を補う目的で混色するのであれば根粒菌からの栄養補給ができるマメ科野菜がおすすめなので平さやいんげんを混植していきます。
トマトの畝にバジルを混植する

バジルはシソ科の野菜で種が小さく、さらに大葉に比べると発芽率が悪いイメージなのでちゃんと発芽してくれるかどうか不安でしたがいい感じに成長してくれました。
根もいい感じに張っていますが、このまま定植するわけにもいかないのでばらしていきます。

大葉もさし穂がしやすい強い野菜なのでバジルも同じようなものと考え、ざっくりと根をばらして定植していきます。
バジルは水をよく吸い上げるのでトマトが水っぽくなりにくくなるため、結果としてトマトが甘く育つことがコンパニオンプランツとしての効果です。
また、トマトはアレロパシー効果が強いので他の雑草が育ちにくい特徴がありますが、バジルはトマトのアレロパシーにやられずに元気に育ってくれるのもポイント。
WEB情報で知っているだけなので、アレロパシー効果については定量的には説明できませんがたしかにトマトの畝は他の畝に比べると雑草がはびこるようなことは少ないですね。

トマトとバジルの混植はこんな感じです。
バジルはトマトのコンパニオンプランツではあるんのですが、うちの場合は畝間スペースは狭く、さらにトマトを密植栽培してしまうのでトマトの畝と畝の間は日当たりが悪くなりがちです。
乾燥バジルやバジルペーストなど使い勝手抜群なのでしっかりと育ってもらいたいので、今回は畝の両端に植えることで日当たりを確保しました。
トマトとマメ科の平さやいんげんを混植して窒素を補給

バジルはトマトの味をよくするためのコンパニオンプランツですが、マメ科野菜は根粒菌が窒素を固定してくれるためトマトへの栄養の補給をおこなってくれるコンパニオンプランツになります。
施肥量を減らすことができるしトマトも生育がよくなるのでマメ科野菜との混植はメリットしかありません。
今回混植するのは年に3回ほど栽培できる平さやいんげんです。トーホクからはモロッコインゲンの名前で販売されています。
ポットで育苗してから定植しようかなと思っていたのですが、枝豆以外のマメ科野菜は発芽~苗が育つまで少し時間がかかるのでトマトを定植する際に畝に種まきしていました。
トマト2株に1株くらいを目安に種まきしましたが、いい感じに発芽してくれています。
ただ、昨年は日当たりがイマイチだったのかあまり収穫できなかったのが気がかりです。
栄養補給要因なので、生育は悪くてもOKですが生育が悪いということは窒素の固定も悪くなるので今年はよーく観察しておきたいと思います。
トマトはたわわに実り、いんげんは伸びきったので摘心しました

植え付けた当初は生育が緩慢でちょっと不安でしたが、気温も上がって雨の量が増えてきた当たりからグングンと成長し始め、今ではこんな感じにたわわにトマトが実っています。
完熟するのが待ち遠しいですが、一部、ミニトマトだったはずなのにやけに大きい実がなっている株もあります。
種を間違えていたら大玉トマトの割合が増えそうですね…うちの家はミニトマトの方が人気なので若干不安です。

平さやいんげんも支柱のてっぺんまで伸びきったので摘心して脇芽の発生を促します。
平さやいんげんの収穫は始まっていますが、今年は結構な数の平さやいんげんを植えたので取れすぎるくらいの収穫が期待できます。
平さやいんげんは大きくなりすぎると硬くて食べられなかったので若取りを意識して収穫していきますが、週末くらいしか収穫できないので取るときは大量になっちゃうのが嬉しい悲鳴です。
コンパニオンプランツも混植してトマトを栽培しよう
今回はトマトの定植方法とコンパニオンプランツの混植について紹介しました。
夏野菜の定番のトマトは種から発芽させて育苗していく過程は手がかかるものの、定植までしてしまえばあとはグングン育ってくれます。
鈴なりのトマトがなっているのを眺めるのもワクワクするので栽培していて楽しい野菜ですね。
うちの家庭菜園は自然農に近い形を目指して有機栽培しているので雑草も比較的はやしっぱなしですし、畝にはメインとなる野菜だけでなくコンパニオンプランツも積極的に混植しています。
トマトのコンパニオンプランツといえばバジルですが、マメ科の平さやいんげんも一緒に植えることで味と生育の面からサポートしていく計画です。
家庭菜園だからこそ手間をかけ、工夫して栽培していくこともできるのが楽しいですね。
みなさんもぜひ参考にしてみてください。
【初心者でもできる】完熟したトマトから翌年用の種を採取と保管方法








コメント